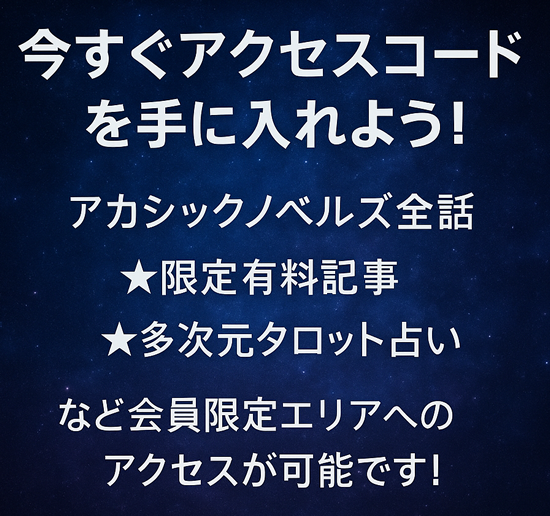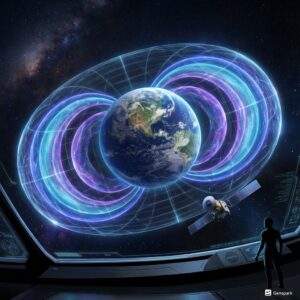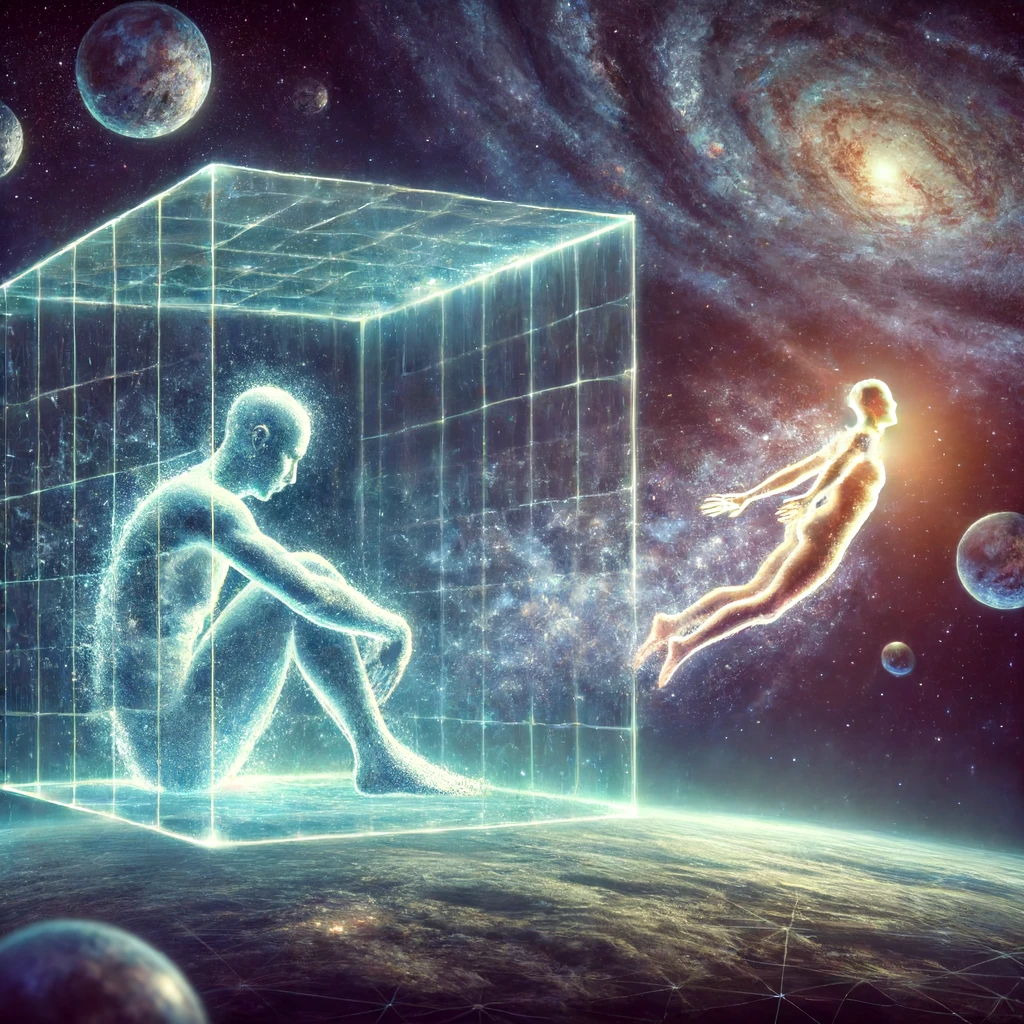あなたの知らない世界の扉
もし、あなたの見慣れた日常が、ほんの些細なきっかけで崩れ去るとしたら?
例えば、いつも座っているリビングのソファ。その壁との間にできた、ほんの数センチの薄暗い隙間。普段なら気にも留めないその空間が、もし、全く別の世界、二度と戻れないかもしれない異界への入り口だとしたら…?
これは、単なる子供だましのホラ話ではありません。今、インターネットの深淵から生まれ、世界中の人々を虜にしている新しい都市伝説の核心に触れる問いかけなのです。その名は「The Backrooms」。そして、その入り口とされるのが「リミナル空間」です。
この記事では、単なるインターネットミームとして片付けられがちなこれらの現象が、なぜこれほどまでに私たちの心を掴んで離さないのか、その謎を深く、深く掘り下げていきます。それは、人間の心の奥底に眠る根源的な恐怖と、抗いがたい魅力の物語。
読み終えた後、あなたの周りの世界は、もう昨日までと同じには見えないかもしれません。壁のシミ、誰もいない廊下、点滅する蛍光灯…。そのすべてが、あなたを異界へと誘う「ゲート」に見えてくるかもしれないのですから。
さあ、覚悟はよろしいですか? 私たちの現実が、いかに脆く、不確かなものであるかを暴く旅へ、ご案内しましょう。
第一章:リミナル空間とは何か? – 日常に潜む「間の空間」の不気味さ
この奇妙な旅を始めるにあたり、まず理解しなければならない重要な概念があります。それが「リミナル空間(Liminal Spaces)」です。この言葉を聞いたことがない人も、おそらく無意識のうちに、その空間の持つ独特な空気に触れた経験があるはずです。
「リミナル」という言葉の語源は、ラテン語の「limen(リーメン)」、すなわち「敷居」や「境界」を意味します。つまりリミナル空間とは、文字通り「境界にある空間」「過渡的な空間」のこと。それは、明確な目的を持つ「出発点」でも「目的地」でもなく、その二つの間に存在する、いわば「通過点」として設計された場所を指します。
具体的に、どのような場所がリミナル空間にあたるのでしょうか。想像してみてください。
- 深夜、誰もいなくなった学校の廊下。 昼間の喧騒が嘘のように静まり返り、窓から差し込む月明かりだけが床を照らしている。本来そこにいるはずの生徒や教師の気配が完全に消え去り、空間そのものがまるで別の目的を持って存在しているかのように感じられます。
- 早朝のショッピングモール。 シャッターはまだ閉ざされ、BGMも流れていない。天井の蛍光灯だけが煌々と点灯し、マネキンだけが静かにこちらを見つめている。活気という魂を抜かれた巨大な空間は、ただただ不気味な沈黙を保っています。
- 霧が立ち込める、広大な駐車場の片隅。 遠くの街灯はぼんやりと滲み、自分の車の隣がどうなっているのかすら判然としない。ここはどこで、どちらへ向かえばいいのか。方向感覚と現実感が曖昧になっていく感覚。
- 地方の空港の、利用者の少ない待合室。 硬いプラスチックの椅子が整然と並び、フライト情報を告げる無機質なアナウンスだけが時折響く。誰もが「どこかへ行くため」に一時的に滞在するだけで、この場所に根差している者は一人もいない。
その他にも、深夜のコインランドリー、病院の待合室、ホテルの長い廊下、誰もいない駅のホーム、子供の頃に遊んだ公園の遊具が寂しく佇む夕暮れ時など、例を挙げればきりがありません。
では、なぜこれらの「間の空間」は、私たちの心にこれほど奇妙で、しばしば不安を伴う感情を呼び起こすのでしょうか。その理由は、いくつかの心理的な要因に分解できます。
一つは**「不在感」**です。これらの空間は、本来、人々が活動し、コミュニケーションをとるために存在します。しかし、リミナル空間として認識されるとき、そこからは「人」という最も重要な要素が欠落しています。魂を抜かれた肉体のように、本来の目的を失った空間は、見る者に言いようのない喪失感と違和感を与えるのです。脳が「ここには誰かいるはずだ」という予測を立てるのに対し、現実は「誰もいない」という事実を突きつける。この認知的な不協和が、不気味さの源泉となります。
二つ目は**「過渡性」**です。私たちは常に、ある状態から次の状態へと移行しながら生きています。リミナル空間は、その「移行の途中」という状態を物理的に具現化したものです。そこは安住の地ではなく、あくまで一時的な通過点。そのため、私たちは本能的に落ち着かず、漠然とした不安を感じます。いつまでも廊下に立ち尽くしているわけにはいかない、早く目的地に着かなければならない、という焦燥感。しかし、その目的地が見えないとき、不安は恐怖へと変わっていきます。
そして三つ目が、**「ノスタルジアと不気味さの同居」**です。リミナル空間の画像や映像の多くは、少し古びた、80年代や90年代を彷彿とさせる雰囲気を持っています。これは、多くの人々が子供時代を過ごしたであろう時代の風景であり、一見すると懐かしさ(ノスタルジア)を覚えます。しかし、その懐かしい風景から人の気配だけが消えている。楽しかったはずの記憶が、どこか歪んで、不気味なものとして立ち現れる。この感覚は、精神分析学者のフロイトが提唱した「不気味なもの(Das Unheimliche)」の概念、すなわち「よく知っている親しいものが、抑圧によって疎遠になったもの」という定義と酷似しています。知っているはずなのに、何かが決定的に違う。このズレこそが、私たちの心を強くざわつかせるのです。
リミナル空間は、いわば日常と非日常の境界線です。普段は意識することなく通り過ぎているだけの場所。しかし、ひとたび足を止め、その空間が持つ本来の意味が剥ぎ取られた姿を直視したとき、私たちはそこに異界への入り口、つまり「ゲート」の存在を幻視してしまうのかもしれません。そして、そのゲートの先に広がっているのが、インターネットが生んだ最恐の都市伝説、「The Backrooms」なのです。
第二章:The Backroomsの誕生 – インターネットが生んだ最恐の都市伝説
リミナル空間という概念が、日常に潜む静かなる恐怖の「前触れ」だとしたら、「The Backrooms(バックルーム)」は、その扉を開けてしまった者が迷い込む、悪夢そのものです。この都市伝説は、どのようにして生まれ、なぜこれほどまでに爆発的に広まっていったのでしょうか。その起源は、インターネットの匿名掲示板へと遡ります。
物語は2019年5月12日、アメリカの匿名画像掲示板「4chan」の超常現象板(/x/)から始まりました。あるユーザーが、「不穏な画像(disquieting images)」を投稿するよう呼びかけるスレッドを立てました。様々な不気味な画像が投稿される中、一人の匿名ユーザーが、一枚の奇妙な写真を投稿します。
その写真は、少し傾いたアングルから撮影された、だだっ広い部屋を写したものでした。壁は、シミのついた単調な黄色の壁紙で覆われています。床には、湿っていそうな薄汚れたベージュのカーペット。天井には、オフィスでよく見かける蛍光灯が、ブーンという低いハム音を立てていそうな雰囲気で、等間隔に並んでいます。部屋には窓も家具もなく、ただただ同じような風景が奥へと続いているように見えました。どこかの古いオフィスのバックヤードか、あるいは取り壊し前の建物のようにも見えますが、異様に生活感がなく、人間的な温かみが一切感じられない、ひどく無機質な空間でした。
この写真だけでも十分に不気味でしたが、この投稿の真価は、写真に添えられた短いテキストにありました。それは、まるでこの世界に迷い込んでしまった者からの警告のような、怪談(クリーピーパスタ)でした。
“If you’re not careful and you noclip out of reality in the wrong areas, you’ll end up in the Backrooms, where it’s nothing but the stink of old moist carpet, the madness of mono-yellow, the endless background noise of fluorescent lights at maximum hum-buzz, and approximately six hundred million square miles of randomly segmented empty rooms to be trapped in.God save you if you hear something wandering around nearby, because it sure as hell has heard you.”
(日本語訳)
「もし君が注意を怠り、おかしな場所で現実から『ノークリップ』してしまったら、行き着く先はバックルームだ。そこにあるのは、古くて湿ったカーペットの悪臭、単調な黄色の狂気、最大音量で鳴り響く蛍光灯の無限のハム音、そして、ランダムに区切られた約6億平方マイル(約10億平方キロメートル)もの空っぽの部屋々だけ。もし近くで何かが歩き回る音を聞いてしまったら、神のご加護を。なぜなら、そいつは確実に君の音を聞いているのだから」
この投稿は、瞬く間に掲示板のユーザーたちの心を鷲掴みにしました。特に秀逸だったのが**「ノークリップ(noclip)」**という言葉の引用です。これは元々、ビデオゲームの用語で、プレイヤーキャラクターがバグやチートによって壁や床をすり抜けてしまい、通常では行けないマップの裏側(文字通りバックルーム)に落ちてしまう現象を指します。この誰もが知るゲーム用語を現実世界に持ち込むことで、「現実というゲームにもバグがあり、ふとした瞬間に裏世界へ落ちてしまうかもしれない」という、恐ろしくも правдоподобной(ありえそう)な恐怖の概念を提示したのです。
この最初の投稿が定義した「The Backrooms」の基本設定は、極めてシンプルでありながら、想像力を刺激する要素に満ちていました。
- 無限の空間: 約6億平方マイルという、天文学的な広さ。これは脱出が絶望的であることを示唆しています。
- 単調な風景: どこまで行っても続く黄色い壁と湿ったカーペット。この単調さは、人間の精神を徐々に蝕んでいきます。
- 不快な環境音: 常に鳴り響く蛍光灯のノイズ。完全な沈黙よりも、この無機質な音が続く方が、より強い精神的苦痛を与えます。
- 未知の存在: 「何か」がいる。その正体は明かされません。姿が見えないからこそ、恐怖は無限に増幅されます。「そいつは確実に君の音を聞いている」という一文は、この空間では生存者こそが「異物」であり、常に狙われる立場にあることを暗示しています。
この都市伝説の真に恐ろしい点は、その**「普遍性」**にあります。写真に写っている風景は、世界のどこにでもあるような、変哲もないオフィスの廊下です。誰もが一度は見たことがある、あるいは働いたことがあるかもしれない場所。だからこそ、人々は「自分の職場も、一歩間違えればバックルームに繋がっているのではないか?」という身近な恐怖を感じることができたのです。
このたった一つの投稿をきっかけに、「The Backrooms」の世界はユーザーたちの手によって爆発的に拡張されていきました。人々は、オリジナルの黄色い部屋を「レベル0」と名付け、さらにその先に広がる様々な世界の「レベル」を創作し始めました。配管が張り巡らされた工業地帯のような「レベル1」、暗闇の駐車場が続く「レベル2」、廃墟と化したオフィスビル「レベル4」。それぞれのレベルには、独自の環境、危険度、そして「エンティティ」と呼ばれる敵対的な存在が設定され、まるで巨大なシェアード・ワールド(共有創作世界)のように発展していったのです。
Reddit、TikTok、そして特にYouTubeでは、この世界観を元にしたショートフィルムやVFX映像、解説動画、さらにはサバイバルホラーゲームなどが次々と生み出され、Backroomsはインターネットカルチャーの一大ジャンルへと成長しました。オリジナルの投稿からわずか数年で、関連コンテンツの総再生回数は数十億回に達すると言われています。
こうして、「The Backrooms」は、匿名の掲示板に投稿された一枚の写真と数行のテキストから、誰もが参加し、誰もが恐怖できる、現代最大級の都市伝説へと変貌を遂げたのです。では、なぜ私たちは、この出口のない悪夢の世界に、恐怖を感じながらもこれほどまでに強く惹きつけられるのでしょうか。次の章では、その心理的な引力について、さらに深く考察していきます。
第三章:なぜ我々は惹かれるのか? – リミナル空間とBackroomsの心理学的引力
リミナル空間の静かなる不気味さと、The Backroomsの絶望的な恐怖。これらは単なるインターネット上の流行り言葉や、一部のマニア向けの怪談話ではありません。これらの概念がこれほどまでに多くの人々の共感を呼び、一種の社会現象にまでなっている背景には、人間の深層心理に訴えかける、いくつかの強力な「引力」が存在します。
1. 見慣れた風景の「異化作用」と「不気味の谷」
私たちの脳は、日常的に接する環境を効率的に処理するため、多くの情報を自動化し、意識から除外しています。毎日通る通勤路の建物の数や、自室の壁のシミの形を正確に覚えている人はほとんどいないでしょう。これらは「見慣れた安全な風景」として、意識のフィルターを素通りしていきます。
しかし、リミナル空間やBackroomsの概念は、このフィルターに強制的に介入し、**「異化作用」**を引き起こします。異化作用とは、見慣れた日常的な物事を、まるで初めて見るかのように奇妙で異質なものとして捉え直させる手法です。例えば、誰もいないオフィスの写真。それは単なる空っぽの部屋ですが、「ここはBackroomsかもしれない」という文脈を与えられた瞬間、私たちはその空間を注意深く観察し始めます。壁のシミは誰かの顔に見え、廊下の奥の暗がりには何かが潜んでいるように感じられる。蛍光灯の明滅は、異界からのモールス信号のように思えてくるのです。
この感覚は、前述したフロイトの**「不気味なもの(Das Unheimliche)」**の概念と深く結びついています。フロイトによれば、最も強い不気味さや恐怖は、全く未知の新しいものではなく、「かつて親しかったが、抑圧されたものが回帰してきた」ときに生じます。リミナル空間が喚起するノスタルジー(懐かしさ)は、まさにこの「かつて親しかったもの」です。しかし、そこから生命感や人間性が奪われている。この僅かな、しかし決定的なズレが、私たちの心の奥底にある不安を掻き立てるのです。それは、人間そっくりに作られたアンドロイドが、ある一点を超えると急に不気味に見える「不気味の谷現象」にも似ています。現実に限りなく近いからこそ、その僅かな非現実性が際立ち、恐怖となるのです。
2. コントロール不能な状況への恐怖と、秩序からの逃避願望
現代社会は、合理性、効率性、そして予測可能性によって成り立っています。私たちはGoogleマップで行き先を正確に把握し、スケジュールアプリで分刻みの予定を管理し、天気予報で明日の天候を予測します。私たちの生活は、世界を「コントロール可能」なものとして捉えることで、安定と安心を得ています。
The Backroomsは、この現代社会の価値観を根底から覆す世界です。そこには地図もなければ、出口の保証もありません。法則性はランダムで、時間は歪み、空間は無限に広がっています。努力が報われるとは限らず、理不尽な死がすぐそばにあります。これは、私たちが最も恐れる**「コントロール不能な状況」**の究極的な形です。
しかし、逆説的ですが、このコントロール不能な状況は、ある種の人々にとっては魅力的に映ります。常に社会的なルールや期待に応え、予測可能な日常を繰り返すことに疲弊した人々にとって、Backroomsはすべてをリセットできる「無秩序な世界」として機能するのです。そこでは学歴も職歴も社会的地位も意味をなしません。問われるのは、ただ生き延びるための本能的な力だけです。この過酷なサバイバル状況への没入は、日常のしがらみや責任からの**「逃避願望」**を刺激し、一種のカタルシス(精神の浄化)をもたらすのです。安全な現実世界から、恐怖の世界を「鑑賞」することで、人々は日常のストレスを相対化し、解放感を得ているのかもしれません。
3. 集合的無意識と共有されるノスタルジア
カール・ユングは、人間の無意識には個人的な領域を超えた、人類共通の元型(アーキタイプ)が存在する「集合的無意識」の層があると提唱しました。リミナル空間やBackroomsの画像が喚起する感覚は、この集合的無意識に触れている可能性があります。
多くの人が、これらの画像を見て「どこかで見たことがある」「子供の頃、こんな場所に行ったことがある気がする」という、デジャヴュに似た奇妙な感覚を覚えます。それは特定の個人の記憶というよりも、人類が進化の過程で経験してきた「洞窟」「迷宮」「誰もいない荒野」といった元型的なイメージの断片を呼び覚ましているのかもしれません。出口のない迷宮(ラビリンス)の神話は世界中に存在し、それは未知への恐怖と探索への欲求という、人間の根源的なテーマを扱っています。
また、より現代的なレベルでは、**「共有されるノスタルジア」**が大きな役割を果たしています。特に80年代から2000年代初頭にかけての、デジタル化され尽くす前のアナログな時代の風景(ブラウン管テレビ、古いPC、ビデオテープの画質など)は、ミレニアル世代やZ世代にとって、直接経験していなくても、メディアを通じて「懐かしい」と感じる対象となっています。この時代の風景は、インターネットがまだ普及しきっておらず、世界のすべてが可視化されていなかった「未知の余白」があった時代を象徴しています。Backroomsの世界観は、この失われた時代のノスタルジアを巧みに利用し、多くの人々の集合的な記憶(あるいは記憶のイメージ)に訴えかけることで、強固な共感の土台を築いているのです。
4. 探索と創造の欲求を満たす「オープンワールド」
The Backroomsの物語は、最初の投稿で完結しませんでした。むしろ、それは壮大な物語のプロローグに過ぎませんでした。ユーザーたちは次々と新しい「レベル」や「エンティティ」、「派閥」や「アイテム」などを創作し、ウィキサイト「Backrooms Wiki」などを通じて、その世界観を共同で構築し続けています。
これは、人間の根源的な**「探索と創造の欲求」**を強く刺激します。私たちは未知の世界の地図を埋め、その法則を発見し、物語を紡ぐことに喜びを感じる生き物です。Backroomsは、そのための巨大なキャンバス、あるいはオープンワールドのビデオゲームの舞台を提供してくれました。参加者は、単なる恐怖の受け手ではなく、世界の創造主の一員となることができるのです。自分が考えたエンティティが公式設定として認められたり、自分の書いた探検日誌が多くの人に読まれたりする。このインタラクティブな性質が、コミュニティを活性化させ、都市伝説を単なる「噂話」から、生きて成長し続ける「神話体系」へと昇華させたのです。
これらの心理的な引力が複雑に絡み合うことで、リミナル空間とThe Backroomsは、私たちの心の最も原始的で、最も深い部分を揺さぶります。それは、日常の裏側に潜む混沌への恐怖であり、同時に、そこへ足を踏み入れてみたいという抗いがたい好奇心でもあるのです。では、その入り口は、本当に私たちのすぐそば、「リビングの隙間」に存在するのでしょうか。
第四章:リビングの隙間は「ゲート」なのか? – 都市伝説と現実の境界線
さて、私たちはこの奇妙な旅の核心へとたどり着きました。この記事のタイトルでもある「リビングの隙間は異界の入り口なのか?」という問いです。もちろん、物理的に壁の隙間を通り抜けて、黄色い壁紙の無限回廊に迷い込む、などということが現実で起こると主張するつもりはありません。しかし、この問いは、単なる比喩以上の、深い意味をはらんでいます。
ここで言う**「リビングの隙間」とは、物理的な空間だけを指すのではありません。それは、私たちの「意識の隙間」**であり、日常という強固に見える現実の連続性が、ふと途切れる瞬間のメタファーなのです。
考えてみてください。あなたはこれまでの人生で、次のような経験をしたことはありませんか?
- 夜中にふと目が覚めた瞬間。 まだ頭が完全に覚醒していない朦朧とした意識の中で、見慣れた自室の家具の配置が、なぜか全く違う、見知らぬ部屋のように感じられたこと。影が奇妙な形を作り出し、クローゼットの扉が僅かに開いているのが、言いようもなく不気味に思えた経験。
- 考え事をしていて、上の空で道を歩いていた時。 ふと我に返ると、自分が今どこを歩いているのか、どちらへ向かっていたのかが一瞬わからなくなる。周りの風景が急に色褪せて、まるで映画のセットのように非現実的に感じられる感覚。
- 誰もいないはずの家で、二階から微かな物音が聞こえたような気がしたこと。 「気のせいだ」と自分に言い聞かせながらも、心臓がどきりとし、家の中の空気が一変する。すべての物音が、侵入者の気配に聞こえてしまう。
- エレベーターに乗って目的の階のボタンを押したのに、なぜか全く違う階で扉が開いたこと。 そこは自分が知らないフロアで、薄暗く、静まり返っている。一瞬、自分がいる建物の構造そのものが信じられなくなるような、眩暈に似た感覚。
これらすべての瞬間が、いわば「意識のノークリップ」です。私たちの脳は、常に過去の経験と現在の知覚情報を統合し、「安定した現実」という物語を構築し続けています。しかし、疲労、ストレス、あるいは単なる偶然によって、この統合プロセスに僅かな「バグ」が生じることがあります。その瞬間、私たちは現実というプログラムの裏側、普段は隠されている世界の基盤を垣間見てしまうのです。
そのとき、壁のシミはもはやただの汚れではなく、異界の地図に見え、ドアの向こうの暗闇は、ただの暗闇ではなく、未知の空間への入り口に感じられます。家具と壁の間にできた薄暗い「隙間」は、この現実世界の綻び、別の次元が漏れ出してきている亀裂の象徴となります。これこそが、リミナル空間とBackroomsが、私たちの日常と地続きであると感じられる理由です。それは超常現象ではなく、私たちの**「認識」**の問題なのです。
都市伝説とは、そもそもそういう性質を持っています。それは、私たちが暮らす社会や時代が抱える、言葉にならない漠然とした不安を掬い上げ、具体的な物語の形を与える「鏡」の役割を果たします。
例えば、「口裂け女」の伝説が流行した時代、それは子供たちが学習塾などで夜遅くまで一人で出歩くことが増えた社会の、見知らぬ他人への漠然とした恐怖を反映していました。「人面犬」は、バブル経済期の過剰な開発と環境破壊によって、行き場を失った動物たちの怨念や、非人間的な都市生活への不安が形になったものかもしれません。
では、「The Backrooms」という現代の都市伝説は、何を映し出しているのでしょうか。
一つには、先行きの見えない現代社会への閉塞感と不安が挙げられます。どこまで行っても同じ風景が続き、出口が見えないBackroomsの世界は、まるで終わりのない単調な仕事を繰り返し、将来の展望が見えないまま年を重ねていく現代人の人生のメタファーのようです。「レベル0」と呼ばれる最初のステージが、まさに「オフィス」のような空間であることは、決して偶然ではないでしょう。私たちは皆、知らず知らずのうちに、自分だけの「バックルーム」に迷い込んでいるのかもしれません。
また、常にオンラインで繋がっている世界への疲れも関係しているかもしれません。SNSやメッセージアプリによって、私たちは24時間他者と接続され、プライベートな時間や空間が侵食され続けています。そんな中で、誰もおらず、誰とも繋がれない、完全に孤立したBackroomsの世界は、皮肉にも一種の「聖域」として、歪んだ魅力を持つことがあります。それは、究極の孤独という恐怖であると同時に、社会的ないがらみから完全に解放された、究極の自由でもあるのです。
リビングの隙間は、ゲートです。しかし、それは異次元への物理的な入り口ではありません。それは、私たちの日常がいかに脆く、不確かで、少し視点を変えるだけで全く別の貌を見せるものであるか、という真実に気づかせてくれる「認識のゲート」なのです。この都市伝説は、私たちに問いかけています。「お前の見ている現実は、本当にすべてなのか?」と。そして、一度その問いを投げかけられてしまったら、もう私たちは、無邪気に世界を信じることはできなくなるのです。
結論:扉はいつも開いている
私たちは、「リミナル空間」という日常の裂け目から始まり、「The Backrooms」というインターネットが生んだ巨大な迷宮へと至る、奇妙な旅をしてきました。
この旅を通して見えてきたのは、これらの現象が単なる一過性のブームではない、ということです。それは、見慣れた日常の裏側に潜む非日常への恐怖と憧れ、既知の世界から未知の世界へ足を踏み入れたいという根源的な欲求、そして、自分たちが生きるこの現実そのものへの揺らぎといった、極めて普遍的な人間の心理に根差しています。
リミナル空間は、私たちに「当たり前」を疑う視点を教えてくれます。いつも通り過ぎるだけの廊下、誰もいない待合室。それらの空間が持つ本来の意味を剥ぎ取り、その「空虚さ」そのものと向き合ったとき、私たちは世界の別の側面を知覚します。
そしてThe Backroomsは、その先にある可能性の物語です。それは、現実から滑り落ちてしまった者の悪夢であり、コントロール不能な混沌の世界です。しかし同時に、それは参加者たちの想像力によって無限に拡張され続ける、壮大な共同創作の舞台でもあります。人々は恐怖を感じながらも、その世界の地図を描き、物語を紡ぐことに魅了されているのです。
リビングの隙間、クローゼットの奥の暗闇、夜中の廊下の静寂。
異界への扉は、特別な場所にあるわけではありません。それは、私たちの日常の中に、そして私たちの意識のすぐ隣に、いつも口を開けて待っています。
この記事を読み終えた今、あなたの周りを見渡してみてください。何か、昨日までとは違って見えませんか?
もし、壁の向こうから微かな物音を聞いてしまったら…
くれぐれも、現実からの「ノークリップ」には、ご注意を。